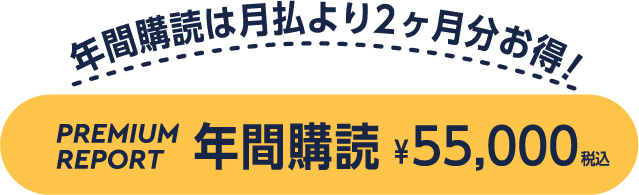パウエル議長の冒頭スピーチの全文翻訳
ありがとう、オースティン。そして、またシカゴに戻って来られてとても嬉しく思います。今日は、私とラジャン教授との対話に入る前に、経済と金融政策の見通しについて簡単に述べたいと思います。
FRBにおいて私たちは常に、議会から課されている二重の使命――最大限の雇用と物価の安定――を達成することに集中しています。現在、不確実性と下振れリスクが高まっている状況ではあるものの、米国経済は依然として堅調な状態にあります。労働市場は最大雇用に近い状態にあり、インフレ率も大幅に低下していますが、依然として2%の目標をやや上回っています。今後発表される第1四半期GDP速報値は2週間ほどで公表される予定ですが、これまでに得られているデータから見ると、昨年の堅調な成長ペースから鈍化しているように見受けられます。
自動車販売は好調でしたが、全体としての個人消費は控えめな伸びにとどまったとみられます。また、企業が関税導入を見越して前倒しで輸入を進めた結果、輸入が増加し、それがGDP成長を下押しする要因にもなりそうです。家計・企業を対象とした調査では、景況感の大幅な悪化と、先行きへの高い不確実性が報告されています。これは主に、貿易政策への懸念が反映されたものでしょう。年間の成長率見通しも下方修正が相次いでおり、成長は鈍化するもののプラス圏を維持するとの予測が多く見られます。
労働市場に目を向けると、本年初めの3カ月間で、非農業部門雇用者数は平均15万人の増加となっています。昨年と比べると鈍化していますが、解雇は依然として少なく、労働参加率も安定していることから、失業率は低水準で安定しています。求人件数と失業者の比率は、依然として1をわずかに上回っており、パンデミック前の水準に近い状態です。賃金の伸びも落ち着きを見せており、インフレを上回る水準を維持しつつ、より持続可能なペースに向かっているといえます。総じて、労働市場は健全な状態にあり、インフレの主要な原因とはなっていないと見ています。
次に物価安定の目標についてですが、インフレ率は2022年半ばのピーク時からは大きく低下しました。 しかも、高インフレを抑制する過程でしばしば見られる深刻な失業率の上昇を伴うことなく、これを成し遂げています。インフレの進展は緩やかに継続しており、直近の指標も目標の2%を上回る水準ではあるものの、引き続き安定的な推移を示しています。先週発表された最新のデータによると、総合PCE価格は前年同月比で2.3%、コアPCEは2.6%の上昇でした(※食品・エネルギーを除く)。
この先の見通しについては、新政権が貿易、移民、財政政策、規制の4分野で大幅な政策転換を進めており、これらの影響はまだ読みきれません。特に関税については、これまでに発表された規模が想定を大きく上回るものであり、今後の経済的影響も同様に大きくなる可能性があります。このような関税政策は、インフレを一時的に押し上げる要因となることはほぼ確実であり、影響が長引けば持続的なインフレにつながるリスクもあります。
インフレの持続性は、以下の要素によって左右されます:
- 関税の規模
- 価格への転嫁が完了するまでの期間
- 期待インフレがどれだけ安定しているか
私たちFRBの責務は、こうした事象が一時的な価格上昇にとどまり、持続的なインフレへと転化しないようにすることです。そのためには、長期的なインフレ期待を確実に安定させ続けることが重要であり、これを成し遂げるために最大限の努力を続けていきます。我々が目指すのは、「価格の安定なくして、誰にとっても恩恵のある長期的な強い労働市場を維持することはできない」という基本原則に基づく政策運営です。今後、物価安定と最大雇用という二つの目標がトレードオフの関係に置かれる可能性もあります。その際には、両者の乖離の大きさと、それぞれが収束するまでの時間軸を慎重に見極めながら判断していきます。
しばしば引用されるシカゴ出身の哲人フェリス・ビューラーの言葉を借りれば、
“Life moves pretty fast.”(人生はあっという間に過ぎていく)
現時点では、状況のさらなる明確化を待つのに十分なポジションにあると考えています。今後も引き続き、入ってくるデータ、経済の見通しの変化、リスクのバランスを丁寧に分析し、最大限の雇用と物価安定の実現に向けて取り組んでいきます。
パウエル議長、リベラル経済観に対する沈着な勝利
2025年4月16日、イリノイ州シカゴで行われた経済クラブ講演において、FRBのジェローム・パウエル議長は、約1時間にわたる公開対談で米国経済と金融政策に関する見解を語った。モデレーターは、元IMFチーフエコノミストであり、インド準備銀行前総裁のラグラム・ラジャン氏。インドで金融政策を担当していた彼が、冒頭「金利はコイントスで決める」などとジョークめかして話を振ったのは象徴的だった。
対談は終始、“言質を取りたいモデレーター” vs “役者の違いを見せるパウエル議長”という構図で進んだ。
言質狙いの質問、しかしパウエル議長は動じない
モデレーターは、次々と以下のような「踏み絵的質問」を議長に投げかけた:
-
「関税がインフレを引き起こすなら、利上げの必要はありますか?」
-
「構造的な政策転換が不確実性を高めているが、どう対応するのか?」
-
「景気後退とインフレの同時発生なら、FRBはどちらを優先するのか?」
これらは一見すると政策論だが、実際には政権(トランプ政権)の政策を間接的に批判する言質をパウエル議長に引き出す意図が明確だった。
特に、**「Fed Put(株価下支え)」**の存在を問う質問は象徴的で、モデレーターの方から「あなたが何も言えないことを分かった上で、それを“答え”にしてしまう」構図すら見え隠れした。
パウエル議長の応答:政策とは“分析と責任”であり、“反応と誘導”ではない
こうした誘導的質問に対して、パウエル議長は決して乗らなかった。
彼は終始冷静に、「わかっていること」「わかっていないこと」「今は判断できないこと」を明確に区別しながら、次のように本質を語った。
「私たちの役割は、最大雇用と物価安定という二つの目標を、最もバランスの取れた形で達成することである」
そして、利下げや利上げの時期に言及することなく、次の点を明言した。
-
インフレは目標をまだ上回っているが、持続的とは断定できない
-
関税の影響は一時的か持続的かまだ判別がつかない
-
労働市場は強いが、同時に移民政策や財政不安による不確実性も高まっている
-
今は動くべきタイミングではなく、「より多くの情報を待つ」局面である
つまり、いま金融政策を動かすことが“政治的期待への反応”になってはならないという厳然たる立場を貫いたのである。
「タカ派」認定の滑稽さと、市場の反応主義
対談後、市場では「タカ派的講演」との声が一部で見られたが、これは失望による“逆張りラベリング”に過ぎない。
実際のところ、パウエル議長は一度も「引き締めが必要」と言っておらず、利上げ再開も示唆していない。ただ、「利下げの根拠が今はない」と淡々と述べたに過ぎない。
「利下げが出ない」=「タカ派だった」という判断は、金融政策を“サプライズ期待のゲーム”と捉えている短絡の極みである。
それはちょうど、「試合に勝てなかった監督はすべて戦術ミス」と断ずるような、後出しジャンケンのレトリックだ。
リベラル経済観が抱える“構造的な短期主義”
今回のモデレーターの態度は、リベラル経済観が抱える**「市場を守るためには政策介入を急げ」**という思想の延長にある。
-
不確実性があるから利下げすべき
-
関税は悪だから、それを前提に金融政策も対応せよ
-
科学研究費や公共支出が減るから景気は悪化すると決めつける
これらは一見すると弱者への配慮に見えるが、根本にあるのは“今すぐ結果を出せ”という短期主義的な要求であり、それこそが不確実性を増幅させる要因になっていることを、彼らは認識していない。
「役者が違う」パウエル議長の凄み
最後に、質疑応答の終盤で見られたパウエル議長のある発言が、この対談の勝者を決定づけた。
「我々は、政治的な圧力にも、マーケットの期待にも左右されず、アメリカ国民のために最善の判断を行う」
金融政策とは、見通しではなく責任であり、反応ではなく構造への対応である。
その原則を守り抜くパウエル議長の姿勢は、“何も言わない”ことを最大のメッセージに変える術を知る者の強さである。
終わりに
今回の対談は、FRB議長と元中央銀行総裁という“同業者”同士の知的対話に見せかけながら、実際には政治的思惑と制度的自制のぶつかり合いであった。
しかし終わってみれば、勝敗は明らかである。インド中央銀行が“コイントス”で金融政策を決めていたとしても――FRBは、論理と責任と沈黙で政策を貫く。
そして市場は、その差を理解する責任を持たねばならない。