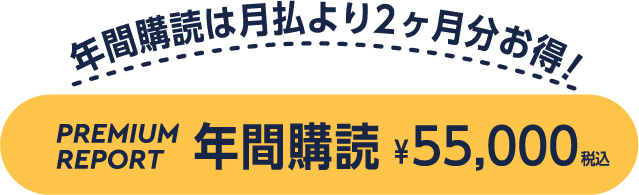NVIDIAのBlackwell世代が正式に立ち上がり、GB200を中心とした次世代インフラが構築されるなか※、市場では「AI投資は終わった」あるいは「AI投資はまだ伸びる」といった議論が今もなお続いています。
しかし業界各社の決算発表をつぶさに見れば、こうした疑問に対する答えは明らかになるでしょう。
今回は特に、2025年4月24日から5月1日までの間に行われた、Alphabet(Google)・Microsoft・Meta・Amazon・Apple各社の発表内容を、プロのファンドマネージャーが解説します。
※詳細は、前回の無料記事「NVIDIA GB200 NVL72の登場による、CSPのインフラ再設計」を参照。
投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。
(Fund Garage編集部)
決算発表の時系列に見るAI時代の主役たち、その次の一手
本記事では、Alphabet(Google)・Microsoft・Meta・Amazon・Apple各社のFY2025Q1決算発表内容を時系列順に振り返っていく。
生成AIの主戦場であるこれらビッグテック5社(GAFAM)がこの四半期で何を語り、何に資金を投じ、どんな戦略を描いたのかを確認していこう。
【Alphabet(GOOG)】── フルスタックの強み
今期のAlphabet(GOOG)の決算は、AIに関しては技術と構造をよく知る人たちには極めて力強く見えた一方、一般の投資家には少し分かりにくい内容だったかもしれない。
その理由のひとつに、ピチャイCEOが冒頭で語った「AIフルスタックの進化」という表現が挙げられる。これは簡単に言えば、AIを「作る」「動かす」「提供する」すべての工程を自社で揃えている状態のこと。たとえば具体的には、
- モデルを設計する →Geminiシリーズ
- それを動かすチップを作る →TPU(カスタムASIC)
- 実行環境(クラウド)を用意する →Google Cloud
- 使いやすく加工して開発者に渡す →Vertex AI、Agent Designer
- 最終的に自社プロダクトで活用 →Google検索・YouTube・広告
といった工程や製品を指す。
<自社製チップ「TPU Ironwood」とNVIDIA Blackwellの関係>
Googleは今期、TPUの最新世代「Ironwood」を初めて推論専用として投入したと明言した。これは、生成AIの“回答する側”としての負荷(推論)を効率的にさばくための専用チップで、従来より10倍の性能、2倍の電力効率を持つとされる。
一方で、Googleはそのすぐ後に、「NVIDIAのBlackwell(B200/GB200)をクラウドで世界最初に提供する」とも発表した。これは一見、「あれ、自社製チップと矛盾してない?」と思われるかもしれないが、ここにGoogleならではの合理的な棲み分け戦略がある。
-
- TPU…自社サービス(YouTube、検索など)で扱う巨大データとモデルを動かす
- Blackwell…一般企業がGoogle Cloudで利用するAI(特に他社製モデル)を提供
つまり、「社内はTPU、外販はNVIDIA」という二重構造なのだ。
<Agent SpaceとAgent Designer>
さらに今期、「Agent Designer」および「Agent Space」という開発者向けツールも新たに発表された。これはいずれも、企業が「自分の業務に合ったAIエージェントを自作できる」ようにするための仕組みで、目的をもって情報を取りに行ったり、操作を実行したり、複数の判断を組み合わせて行動できる存在を指す。
【Microsoft(MSFT)】── Reasoning AIとAgentic AIの日常化を支える、縁の下の力持ち
Microsoftの今期の決算カンファレンスで最も印象的だったのは、AIが単なる流行ではなく、「クラウド上で使われ始めている」という明確な実績の提示だった。
<Azureの成長と自社コスト構造の変革>
2025年1月〜3月の間に、自社クラウドサービス「Azure」を通じて処理されたAIトークンが合計で100兆個に達したと発表(1年前の5倍)。この数字は、AIを本格運用する企業が世界中に急増していることを意味しており、トークン経済はもはや実験段階を超えて、日常業務でReasoning AIを使う段階に突入しつつあることの証明とも言える。
この実需の裏付けとして同時に、10カ国にわたるデータセンターの新設を報告。実際、GPU調達のリードタイムは20%短縮され、AI処理あたりの消費電力は約3割削減、トークン1個あたりのコストは半減した。このように、コスト構造全体をAIに最適化しているという点がMicrosoftらしい。
<FoundryによるAIエージェントの広がり>
また、同社が力を入れる「Copilot戦略」の裏には、「Foundry(ファウンドリー)」という新たなソフトウェア基盤がある。これは、企業や開発者が自社の業務に最適なAIアプリやAIエージェントを設計・運用できる開発プラットフォームを指す。実際、今期だけでもこのFoundry上で10,000を超える企業が独自エージェントの構築を進めたという。
【Meta Platforms(META)】── インフラを持たぬ者が、いかにしてAIビジネスの中心にいるのか
Metaはクラウドサービスプロバイダー(CSP)ではないにも関わらず、このAI時代において中心的プレイヤーの一角を占めている企業だ。
その象徴として、Llamaシリーズに代表されるオープンソース型のLLM(大規模言語モデル)の開発と配布がある。開発者が自由に使えるLLMを世界中にばらまくことで、Meta独自のAI体験を世界に植え付けるビジネス戦略だ。そしてその体験の中に、Metaが保有するインフラが自然と組み込まれていく。
現に、今期の決算ではMeta AIの月間アクティブユーザーが10億人に迫る規模にまで成長していると報告された。これはLlamaを用いたAIが、すでにMetaの主力プロダクトの中に溶け込んでいるという十分な証拠である。
<WhatsAppとInstagramの「ビジネスメッセージエージェント」構想>
今期決算の重要な発表の一つに、WhatsAppとInstagramにおける「AIビジネスメッセージエージェント」の構想がある。これは、企業がAIエージェントを通じて、チャットでの顧客対応・商品提案・予約・販売などを全自動で行う仕組みを提供するというものだ。既存のWebフォームやFAQではなく、人に話しかけるように買い物やサポートを依頼できるチャネルとして、B2Cの新たな体験を提供する。
<スマートグラス「Ray-Ban Meta」>
Metaが注力するもう一つの領域が、「AIを物理的な体験に変換する」ことである。その代表商品が、Ray-Banとの協業によるAI搭載型スマートグラス「Ray-Ban Meta」だ(販売台数は前年同期比で3倍を記録)。MetaはこのデバイスにLlamaベースのAIを搭載し、「目の前のものが何か」「今どこにいるか」「何をすべきか」といったリアルタイムの現実理解をAIに委ねる構想を推し進めている。
【Amazon.com(AMZN)】── 「商品を届ける会社」から、「AIに行動させる会社」へ
Amazonといえば、まず思い浮かぶのはネット通販だろう。事実、同社の売上構成を見れば、北米および国際のEコマース事業が全体の7割以上を占めており、今なお祖業である「商品を届ける事業」が収益の柱である。
今期の決算では、このEC事業が堅調に推移した。特に北米では、物価上昇に伴う販売価格の上昇・プライム会員数の増加・倉庫ネットワークの効率化が寄与した。
こうした中、注目すべきはトランプ政権の復帰とそれに伴う関税政策の再開に対して、Amazonがいち早く備えていた点である。ジャシー CEOは今期の決算説明で、「関税発動を前提に、事前に在庫配置や調達ルートの見直しを行い、無駄な追加コストが発生しないよう手を打っていた」と発言。これは、Amazonが単に物流網を保有しているというだけでなく、政策変化に対応できる経営の俊敏さや現場の柔軟性を兼ね備えていることを表している。
<行動するAIの開発「Nova SDK」>
その中核にあるのが、Amazonが開発したNova SDK(Sonic / Premier / Act)である。※SDKとは、Software Development Kitの略
- Nova Sonic …音声や対話に特化し、リアルタイムな応答を実現
- Nova Premier …より精密な推論と複雑なコンテキスト理解を担う
- Nova Act …Action Graphと呼ばれる構造を用いて、AIに具体的な一連の行動(例:注文処理→確認→発送連携)をさせる
このNovaシリーズは、NVIDIAのCUDAのようなハードウェア制御技術とも、NIMsのようなAPI化された推論サービスとも異なり、よりエンドユーザー寄りのAIモデルとして位置づけられる。AmazonがAlexaの進化版とも言える「行動するAI」構築に向けて、本格的にプラットフォームを整備してきた証左である。
<自社開発チップ「Trainium 2」と「Inferentia 2」>
推論ワークロードの増加に伴い、GPUの確保は全クラウド事業者にとっての共通課題である。Amazonはこの領域において、自社開発のAI専用チップである「Trainium 2」および「Inferentia 2」を前面に押し出した。
- Trainium 2 …学習と推論の両方に対応し、高負荷モデルへの対応力を持つ
- Inferentia 2 …推論専用で、特にコスト効率に優れる
これらのチップの登場によって、コストと電力効率の面でBlackwell世代のNVIDIA GPUと使い分けが可能となり、「NVIDIAを最大限活用しつつも、全てをNVIDIA頼みにしない」という柔軟な体制が築かれている。
【Apple(AAPL)】── 多くを語らないのがむしろAppleらしい決算
今期のAppleの決算説明は、AIというキーワードが溢れる中で、異質とも言えるほど静かだった。他社がGPU調達やエージェント構築、推論ワークロードの急増などを語る中、Appleは「Apple Intelligenceへの投資を継続している。近く詳細を共有する」とだけ述べた。だが、この語らなさこそが、AppleのAI戦略を際立たせているように思えてならない。
<クラウドではなく、“手元で動くAI”という設計思想>
AppleのAIの最も特徴的なポイントは、製品体験に組み込まれたエッジ型AIであるという点だ。
他社のようにNVIDIA製GPUを使用し、クラウドに置かれた巨大モデルにアクセスする構造ではなく、基本的に自社設計のAシリーズおよびMシリーズチップ上に搭載されたNeural Engineを活用し、サーバーに頼らず端末内で完結させる設計思想を貫いている。
この文脈の中で語られた「Apple Intelligence」という言葉は、生成系AIの「外部知能」とは対極にある、「内部知能」としてのAIのあり方を表している。
<5,000億ドルの米国投資>
Appleは近年、米国内への大規模な製造と設計投資を加速させており、今後5年間で5,000億ドルを投じる計画を明らかにしている。この投資には、Apple Silicon開発の拡充・先端パッケージング設備の確保・半導体サプライチェーンの再構築が含まれるとみられ、上記エッジAIの進化と、製造基盤の国内完結化という二つの軸が重なりつつある。
まとめ
- Googleの今期決算は、「社内はTPU、外販はNVIDIA」という二重構造を形成し、企業のインフラ構築・推論運用・エージェント設計という骨組みを着々と整えた四半期だった。
- Microsoftの今期決算は、AIそのものを売るのではなく、AIを「使いこなす場」を売る戦略が見えた。これは、これまでクラウドでOfficeやExcelを提供していた同社が、次は「AIアシスタントの民主化」に挑んでいるとも言い換えられる。
- CSPではないMetaにとって最も重要なのは、Facebook・Instagram・WhatsApp・Threadsといったサービスに「人々がどれだけ長く留まるか」である。そのためにAIを誰でも使える文化的装置として普及させることが、根本的な収益のドライバーとなっている。
- Amazonは今、「リアルに物を届ける会社」から「AIに行動させる会社」へ変わろうとしている。その裏には、関税や物流といった現実社会の変化に対応する実務力とともに、Nova SDKやカスタムチップといった技術的積み上げがあるのだ。
- 今回のApple決算を受けて株価が下落したことは、短期志向の失望を映したものにすぎない。長期的に見ればAppleのAI戦略は「自社チップを使用したエッジAIの発展」という点で一貫しており、さらには製造基盤もアメリカ国内に集結する計画だ。
編集部後記
こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。
公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。
また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。
<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。
有料版のご案内
Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。
これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。
勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。