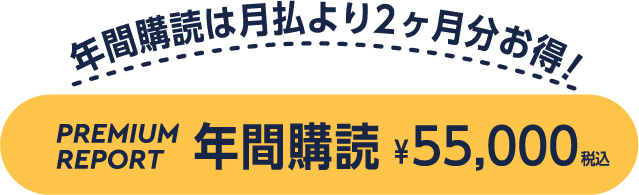現在市場では、トランプ大統領の関税政策や中国制裁などの地政学リスクが叫ばれています。
しかし、世界最大の半導体製造企業である台湾TSMCの2025年第1四半期決算は、そんな市場の悲観論を一蹴したうえで、AI時代の半導体投資について深く考えさせられる内容でした。
今回は、TSMCの2025年第1四半期決算内容を詳しく解説しながら、日本の半導体企業はどのようなことを考えるべきなのか、あるいは半導体業界の構造を私たちは投資家としてどのような視点で見据えていくべきなのかについて、プロのファンドマネージャーがお伝えします。
投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。
(Fund Garage編集部)
TSMCはAIの進化をどう受け止めるか?
悲観論を事実で封じたTSMCの決算
TSMCが発表した2025年第1四半期決算は、現在市場が直面している短期的なノイズに対して、極めて論理的かつ構造的な強気スタンスを貫いた内容であった。
このノイズとは、米国の中国向け製品の輸出規制や関税政策といった地政学的リスクと、一部で囁かれる「AI投資の熱は冷めた」というような懸念だ。
注目すべきは、同社が一貫して強調した以下の3つの論点である。
①AIアクセラレータ需要の継続的な増加
AI向け半導体(GPU・ASIC・HBM)売上高は、2025年中に倍増する見通し。これは過去のFG無料記事※でも指摘してきたように、Reasoning AIの普及がトークン消費を促進し、AI向け半導体をより一層必要とする構造と整合する。
②米国アリゾナ拠点への巨額投資
TSMCは米アリゾナに工場を6つと、2つのパッケージング拠点に加えてR&D(研究開発)センターを新設し、総額1650億ドルという驚異的な規模の設備投資を計画。とりわけ注目すべきは、2nmノード以降(最先端技術)の生産の30%をアリゾナにシフトするという方針だ。これは単なるリスク分散にとどまらず、「TSMC=台湾」という一極依存の構図からの転換を目指していることが窺い知れる。
③外部環境の不確実性への冷静な対応
「米国による半導体関税」「地政学リスク」「インフレによるコスト増」等について、すでに一定のマージン圧迫(年間で2〜3%、後期には3〜4%)を織り込んでおり、主要顧客との価格交渉はすでに始まっていると明言。そのうえで、今のところ顧客の発注行動に目に見える変化はなく、ガイダンスを変更する要因にはなっていないとも強調している。
このようにTSMCは、「AI投資は一巡したのではないか」「地政学リスクが生産を揺るがすのではないか」といった短絡的な悲観論を、ファクト(業績と戦略)によって冷静に否定したと言っていいだろう。
TSMCの発言と行動が物語っているのは、同社が右肩上がりのビジネス・トレンドに立っているという事実であり、それこそが今回の決算における最大の示唆と言えそうだ。
※…「Reasoning AIの普及がトークン消費を促進し、AI向け半導体をより一層必要とする構造」についての過去記事まとめ
🔽Reasoning AIについて
🔽トークンについて
CoWoS供給倍増による日本メーカーへの効果
今回のTSMC決算において、AIアクセラレータの需要増と並んでもう一つ注目すべきは、CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate、コワース)に関する発言である。結論から言えば、TSMCは2025年中にCoWoSの生産能力を倍増させる計画を進めているものの、それでもなお2026年にかけて需給バランスが完全に改善する見込みはないという認識を示した。
C.C. Wei(魏哲家)CEOはCoWoSについて、「以前は“insane(狂ったような)需要”だったが、現在は若干バランスが取れてきた」としつつも、「2026年も需要は依然として高く、供給は追い付かない可能性がある」と明言している。これは単なる言い回しの強弱ではなく、構造的にAIワークロードがCoWoSを必要とする段階が持続するという極めて重要なファンダメンタル認識を表している。
CoWoSとは、先端ロジック(GPUやAI ASIC)とHBMなどの高帯域メモリを高密度で接続する高度な2.5Dパッケージング技術である。とりわけ、AIアクセラレータの演算性能が指数関数的に向上していく流れの中では、HBMとの近接性・帯域の確保が最大の制約条件となるのだが、その解決策がCoWoSなのだ。
つまり、AIモデルが進化すればするほどCoWoSの需要は拡大する構造にあるというのがTSMCの判断である。これもやはり先述の、「Reasoning AIの普及がトークン消費を促進し、AI向け半導体をより一層必要とする」構造を引き継いでいるのだ。
この点は、特に日本株投資家にとって重要な示唆を含んでいる。というのも、現在TSMCやNVIDIA向けにCoWoSやHBMの中核部材を供給している日本企業、たとえば、
- ディスコ(6146):TSMCの先端チップ製造で使われるウエハー切断・研削装置
- アドバンテスト(6857):先端パッケージ向けテスト装置
- 東京応化工業(4186)やJSR(4185):感光材・CMPスラリーといった材料関連
- 住友電工(5802):基板素材や高周波対応材料
- 信越化学(4063)、SUMCO(3436):ウェハー原材料の安定供給
は言うまでもなく、TSMCのCoWoS倍増計画に直接関わってくるからだ。
このようにTSMCの発言は、「AIアクセラレータはピークアウトした」「パッケージング投資は踊り場だ」といった短絡的な観測を否定する内容であり、むしろ2026年にかけて日本の先端装置・材料メーカーにもポジティブな波及効果が継続する構造的根拠を再確認させるものであった。
日本企業に求められる「地理的再適合力」とは?
「2nm以降の生産能力のうち約30%をアリゾナで担う」というTSMCの発表は、従来台湾にほぼ全てを集中させてきた同社の方針を大きく転換するものであり、TSMC自身が自らの先端製造の地政学的リスクを最も重く受け止めていることの現れだといえよう。
この地政学的再配置は、単なる「生産拠点の物理的な分散」にとどまらず、サプライチェーン全体の再構成を意味する。というのも、TSMCはこのアリゾナへの設備投資計画を通して、アメリカ国内に独自の先端半導体エコシステムを築こうとする意図が明確に浮かび上がってくるのだ。
もちろんこの構造変化が、先端材料や装置分野において高い技術力を誇る日本企業に与える影響は少なくない。具体的には、以下のようなサプライチェーン上の再適合(Realignment)が求められると想定される。
① 製造装置メーカーに求められるのは、「現地対応圧力」
東京エレクトロン・ディスコ・SCREEN・アドバンテストなどの製造装置メーカーにとって、アリゾナ新拠点への納入やサポート体制は従来の台湾モデルとは異なるコストと手間がかかる。
さらに、米国政府が掲げる「Buy American」的調達要件への適合や、現地エンジニアによるサポート網の整備も中長期的には求められる可能性がある。
② 材料サプライヤーに求められるのは、「品質保証と物流の再設計」
信越化学・JSR・東京応化工業といった材料メーカーは先端ノードでの採用実績が多いが、アメリカ向けに同等品を供給するには、現地の認証プロセスや再評価の壁がある。
また、湿度や振動などの環境条件が異なる米国内での安定供給を維持するためには、パートナー企業との再連携や現地在庫戦略の強化が求められる。
③ パッケージング系素材に求められるのは、「サプライチェーンの二重構造化」
アリゾナでのCoWoSやSoICなどの高度パッケージ工程が立ち上がることで、日本企業が台湾向けに構築してきた供給体制とは別のロジスティクスが必要となる。
住友電工・ミツミ電機・日立金属といった基板系や接合系素材を扱う企業にとっては、北米拠点の拡充または米系サプライヤーとのアライアンスが中期的な競争力維持に直結する。
このように、TSMCの「アリゾナ2nmシフト」は、日本の材料・装置企業にとって単なる「追い風」ではない。どの企業が台湾依存型のビジネスモデルから、北米を含む地理的多軸体制へと柔軟に移行できるかが、今後の勝敗を分けるファクターとなるだろう。
さらに重要なのは、TSMCがこの構造再編を「臨時対応」ではなく5年、10年スパンでの構造戦略として位置付けている点だ。だからこそ、日本企業にとっても「目先の納入先」ではなく、「どの地域に、どの技術・製品・人材を配置すべきか」という経営レベルの判断が迫られている。
まとめ
- 2025年4月に行われたTSMCの第1四半期決算は、AI投資のピークアウト懸念・米中対立・関税政策・中国制裁といった市場の悲観論がいかに表層的な視点であるかを示唆する内容であった。
- 具体的には、①AIアクセラレータ需要の増加とCoWoS供給の倍増 ②米国アリゾナ拠点への巨額投資 ③地政学的リスクへの対応 について言及。現在のAI革命は依然として成長過程の只中にあるため、むしろ中長期的な設備需要の必要性を再確認する機会となった。
- 特に、「2nm以降の生産能力のうち約30%をアリゾナで担う」というTSMCの発表は、従来台湾にほぼ全てを集中させてきた同社の方針を大きく転換し、アメリカ国内に独自の先端半導体エコシステムを築こうとする意図が明確になった。
- AI進化を受けたTSMC(=製造側)の構造的変化は、先端材料や装置分野において高い技術力を誇る日本企業にも影響を与える。我々投資家は、この流れを無視してはならない。
現在のAI革命は、単なるソフトウェアやアプリケーションの話ではなく、計算需要の構造的転換を伴う。すでに何度もお伝えしているように、かつて生成AI(Training)中心だった投資は現在、推論(Reasoning)→意思決定(Agentic)→物理的実行(Physical AI)へと進化段階を移行しつつあるからだ。
この進化は、単にAIモデルの複雑性を高めるだけでなく、それを支える半導体の微細化・配線密度・消費電力管理等々、あらゆる製造条件を高度化させる。その帰結として、NVIDIAを中核とするAIインフラ投資が「トークン生成の価値」を担保する構造の中で、TSMCは「2nm・CoWoS・北米製造」で拡張しようとする構図ができあがるのだということは理解しておきたい。
市場がこの構造変化を見失い、短期的な地政学ノイズにばかり反応する限り、本質的な投資機会は見過ごされ続けていることになるだろう。
編集部後記
こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。
公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。
また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。
<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。
有料版のご案内
Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。
これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。
勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。