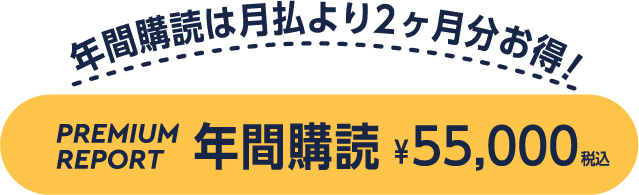セブンイレブンやイトーヨーカドーといった、日本を代表するブランドを持つセブン&アイ・ホールディングス。
ところが現在同社は、巨額の買収提案をカナダの同業大手から受けています。
果たして、日本企業はこれからどんどん弱くなっていくばかりなのでしょうか。プロのファンドマネージャーの視点で解説します。
投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。
(Fund Garage編集部)
驚愕した「カナダからのセブン&アイへの買収提案」
セブン&アイ・ホールディングス(3382)が、カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタール社から買収提案を受けた。なんとその買収提案額は、約7兆円にものぼるという。
このニュースを知って正直、私は我が耳を疑った。「逆の話だろう?」とさえ思ったほどだ。
同時に、日本経済の現状に対して強い危機感を抱かずにはいられなかった。というのも、セブン&アイはかつて日本の小売業界のトップに君臨していた企業だ。それが海外からの買収対象になるというのは、ある程度は個社の経営状況による影響があるのは事実だと思うが、明らかに、日本の経済と消費形態が大きく変化していることも意味する。
日本経済の危機①日本の消費力の弱体化
セブン&アイ・ホールディングスは、イトーヨーカドーとセブンイレブンという強力なブランドを持ち、日本の小売業界を牽引してきた。
2006年、同社は現在のそごう・西武を買収。ところが、その後の統合プロセスや経営戦略において問題が生じた。特に、百貨店ビジネスモデルの再構築に苦労したことが、経営の方向性を曇らせた一因とされる。
そしてこの経営低迷の背景には、日本の消費者行動の変化が深く関与していると考えられる。
1990年代以降、日本経済はデフレに陥り、消費者はより低価格で品質の良い商品を求めるようになった。これが、いわゆるファストファッションやディスカウントストアの台頭を後押ししたのだ。
一方で、高価格帯の商品を扱う百貨店や老舗スーパーは、コスト構造の見直しを迫られ、収益性の低下に直面することとなる。
セブン&アイがこの変化に対応しきれなかった理由の一つに、同社が多様な業態を抱えており、それぞれのビジネスモデルの再編成が十分に進まなかったことが挙げられる。
さらに、デフレ志向の消費が定着したことで、日本の消費市場全体が縮小傾向にあったことも影響しているだろう。これは単にデパートが時代遅れになったということよりも、日本の消費余力そのものが弱まったことを示唆していると考えている。
結局同社は2023年9月、米投資ファンドであるフォートレス・インベストメント・グループにそごう・西武を売却している。同年8月31日には西武池袋本店で労働組合員によるストライキが行われたのも、印象的な出来事であった。
<編集部からの一言>
参考までに、セブン&アイ・ホールディングスの2025年2月期第3四半期(2024年3月~11月)の連結決算は以下のとおりです。
- 売上高:9兆695億9100万円(前年同期比5.7%増)
- 営業利益:3154億100万円(前年同期比23.1%減)
- 純利益:636億3000万円(前年同期比65.1%減)
この決算結果は、主力のコンビニエンスストア事業やスーパーストア事業での減益と、個人消費の低迷が現在も続いていることを浮き彫りにしたと言えるでしょう。
さらに今年3月6日、新社長にスティーブン・デイカス氏を迎えることも発表されました(正式な就任予定は5月27日)。デイカス氏は、日本人の母親を持つ米国出身の実業家で、過去にウォルマート・ジャパン(現西友ホールディングス)最高経営責任者やスシローグローバルホールディングス会長などを歴任しています。
日本経済の危機②日本株の安さ
そしてもうひとつ忘れてはならない重要なことは、日本企業の株価が安過ぎるということだ。
セブン&アイ・ホールディングス(3382)の先週末現在のバリュエーションは、PER※1が24.08倍、PBR※2が1.43倍に過ぎない。
対するイオン(8267)はPERが71.36倍、PBRが3.08倍だ。
まずこのバリュエーションの格差に驚いてしまうが、その理由のひとつが「株主優待」だという。とはいえそれがもし真実ならば、これもまた正直、驚きを禁じ得ないのであるが…。
この事実は、「日本株式市場の値付けの歪み」が露見したことを示している。たとえば日本市場では、「エヌビディア関連銘柄」と称される銘柄が乱舞することも多いが、その関連性は「友達の友達を知っている」程度のものが多いというような意味と、同じように”いびつ”だということ。つまり、「エヌビディアという半導体企業がどうやら爆上がりしているらしい。それなら日本の半導体企業も同様に上がるだろう」みたいなことだ。
トヨタ自動車(7203)のPERが7.32倍で、PBRが1.23倍に過ぎないのも同じことだ。ちなみに、NT倍率※3が現在14.29倍だが、2000年代に遡ると11倍前後に過ぎないということも、ひとつのヒントになるだろう。仮に11倍で再計算すると、今の日経平均株価は29,531円と3万円台にさえ届いていないのだから。
日本最大の時価総額を誇る銘柄の値付けでさえ、この国の資本市場では定量的(合理的)なアプローチは通用せず、定性的(情緒的)なアプローチが全てなのかもしれないということは、以前の無料版ポートでもお伝えした(『トヨタ自動車など「型式指定申請不正問題」の真実』)。
今回のセブン&アイ買収問題のように、海外で通用する商品を持っていながらも株価が上がらない日本企業は、今後海外企業に目をつけられる可能性が高いと言えそうだ。
※1…PER(Price Earnings Ratio)は、「株価収益率」と呼ばれる。「株価÷1株当たりの純利益」の計算式で求められ、株価上昇への期待が高いほど、この数値も高くなる傾向にある。
※2…PBR(Price Book-value Ratio)は、「株価純資産倍率」と呼ばれる。「株価÷1株当たりの純資産」の計算式で求められ、数値が高いほど割高、低いほど割安だと評価される。
※3…NT倍率は、日経平均株価(=N)をTOPIX(=T)で割った数値のこと。現在の市場におけるそれぞれの強さを相対的に知ることができる指標。
まとめ
今回は、セブン&アイの買収で見えてきた問題についてお伝えした。
- セブン&アイ・ホールディングス(3382)が、カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタール社から受けた巨額の買収提案は、日本の経済と消費形態が大きく変化していることを示唆している。
- セブン&アイの経営状況の悪化は、デフレ志向による日本人の消費力の低迷といった、日本経済への警鐘とも言える。
- さらに、日本企業の株価が安すぎることも、海外企業に買収されてしまう大きな要因である。
買収提案を受け、さらに経営陣を新しくするセブン&アイの経営戦略は今後どのように変化していくのだろうか。その結果次第では、他の日本企業も対岸の火事とは言えないだろう。
編集部後記
こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。
公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。
また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。
<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。
有料版のご案内
Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。
これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。
勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。